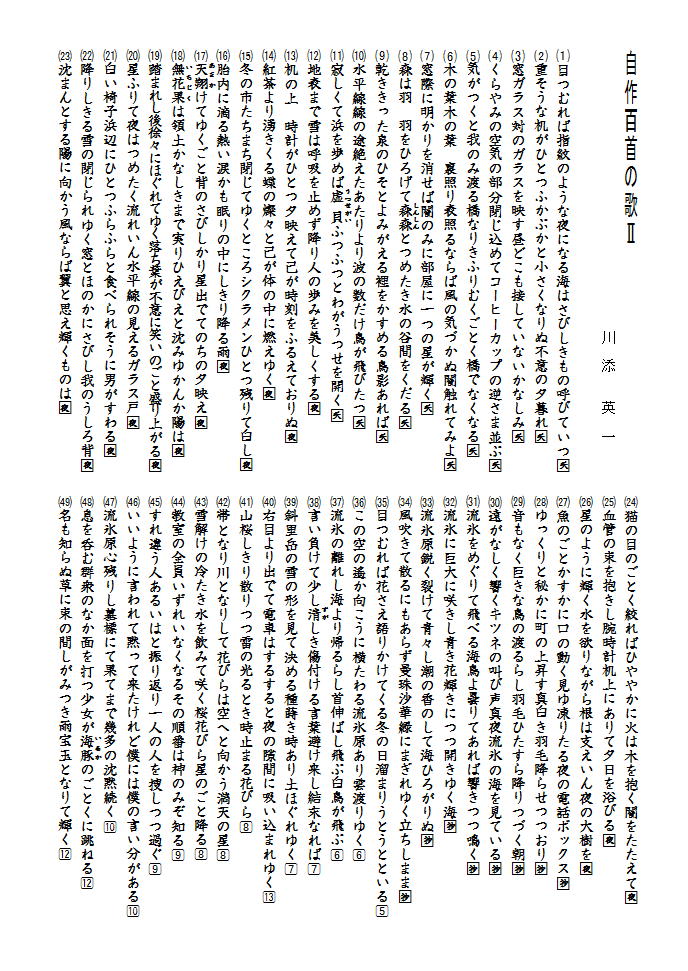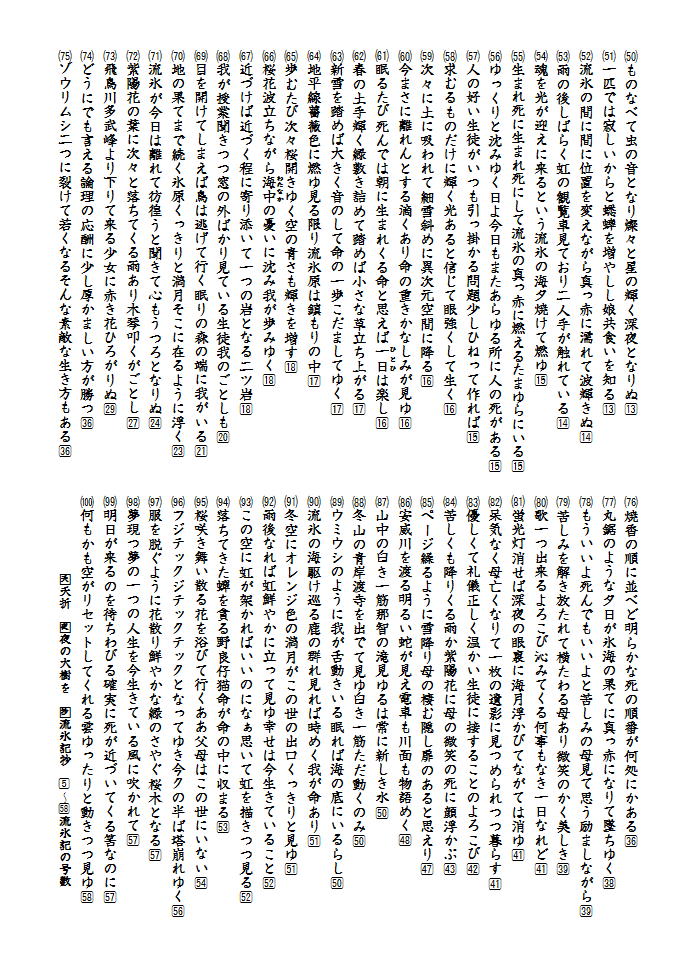流氷が今日は離れて彷徨うと聞きて心もうつろとなりぬ
息を呑む群衆のなか面を打つ少女が海豚のごとくに跳ねる
伸び縮みする時間あり竹刀もてためらわず虚を一気にたたけ
目つむれば指紋のような夜になる海はさびしきもの呼びていつ
たたかれている音深く意識せず明るき雨の舗道に向かう
重そうな机がひとつふかぶかと小さくなりぬ不意の夕暮れ
ゆっくりと闇切り裂いてゆく涙その極点にかかる吊り橋
気がつくと我のみ渡る橋なりきふりむくごとく橋でなくなる
色褪せた花一本の花のため川をのぼってゆく黒き馬
木の葉木の葉 裏照り表照るならば風の気づかぬ闇触れてみよ
窓際に明かりを消せば闇のみに部屋に一つの星が輝く
潜みいる悦びなれば指先に葡萄の房の美しくあれ
地表まで雪は呼吸を止めず降り人の歩みを美しくする
フイルムのような眠りに際やかな蝶となりつつ入る冬の午後
机の上 時計がひとつ夕映えて己が時刻をふるえておりぬ
紅茶より湧きくる蝶の燦々と己が体の中に燃えゆく
冬の市たちまち閉じてゆくところシクラメンひとつ残りて白し
黒枠の四角い夏へ逃走す後なまなまと線路を残し
胎内に滴る熱い涙かも眠りの中にしきり降る雨
水の香の漂う夕べを閉ざしいんまなうら無数の海猫が飛ぶ
草噛みて逃げゆく我に風強き野はにびいろの光さらしつ
夕闇になおも明るく空瓶を吸いつつ白いストロー刺さる
天翔けてゆくごと背のさびしかり星出でてのちの夕映え
無花果は領土かなしきまで実りひえびえと沈みゆかんか陽は
踏まれし後徐々にほぐれてゆく落ち葉が不意に笑いのごと盛り上がる
静かなる海を聞くためはるかはるか双眼鏡を持ち海へ行く
車ののち猫の横切る幾たびか郵便ポストの見える街角
光の束を鍛えるごとし沈まんとする陽の下に聞く槌の音
沈まんとする陽に向かう風ならば翼と思え輝くものは
たちまちにして関わると風のむた雑草群より絮ふかれとぶ
猫の目のごとく絞ればひややかに火は木を抱く闇をたたえて
血管の束を抱きし腕時計机上にありて夕日を浴びる
ゆうやみが酢のごと白くただようと花の下にてひと冷えてゆく
星のように輝く水を欲りながら根は支えいん夜の大樹を
窓ガラス対のガラスを映す昼どこも接していないかなしみ
くらやみの空気の部分閉じ込めてコーヒーカップの逆さま並ぶ
魚のごとかすかに口の動く見ゆ凍りたる夜の電話ボックス
右目より出でて電車はするすると夜の隙間に吸い込まれゆく
帰り道下るは桜通りにて獣の匂いの満つる坂道
次々に桜の枝より放たれて花びら集まるひとところあり
山桜しきり散りつつ雷の光るとき時止まる花びら
雪解けの冷たき水を飲みて咲く桜花びら星のごと降る
帯となり川となりして花びらは空へと向かう満天の星
生徒吐き出でし校舎を見上ぐれば光りつつ雲移動してゆく
生徒にも土にも光が沁みわたりたばしる足の回転が見ゆ
目つむれば花さえ語りかけてくる冬の日溜まりうとうとといる
流氷に巨大に咲きし青き花輝きにつつ開きゆく海
降り続く雪の静寂に洗われて悔いもなく過去よみがえり来る
いいように言われて黙って来たけれど僕には僕の言い分がある
教室の全員いずれいなくなる死ぬ順番は神のみぞ知る
求むるものだけに輝く光あると信じて眼強くして生く
船のごと網走台町潮見町夕日の沈む氷海を行く
次々に土に吸われて細雪斜めに異次元空間に降る
月もなき夜といえども目交いは白き流氷光を放つ
魂を光が迎えに来るという流氷の海夕焼けて燃ゆ
一匹では寂しいからと蟋蟀を増やしし娘共食いを知る
金木犀に雀騒げば明るくて障子に映りし影消えている
雨の後しばらく虹の観覧車見ており二人手が触れている
潮干きてだんだら残る砂浜に白き鳥わが心をつつく
キタキツネ歩みしのみの流氷原その下にして育つ魚あり
ゆっくりと秘かに町の上昇す真白き羽毛降らせつつおり
音もなく巨きな鳥の渡るらし羽毛ひたすら降りつづく朝
踏むたびに我が足音の響くらし崩れつつ立つ流氷の見ゆ
遠がなしく響くキツネの叫び声真夜流氷の海を見ている
流氷原鋭く裂けて青々し潮の香のして海ひろがりぬ
風吹きて散るにもあらず曼珠沙華緑にまぎれゆく立ちしまま
我もまた無数の枝を伸ばしつつ紅あざやかな木と真向かいぬ
この空の遙か向こうに横たわる流氷原あり雲渡りゆく
流氷の離れし海より帰るらし首伸ばし飛ぶ白鳥が飛ぶ
言い負けて少し清しき傷付ける言葉避け来し結末なれば
しおしおと帰れば妻にも言い負けて一人座りぬ氷塊のごと
すれ違う人あるいはと振り返り一人の人を捜しつつ過ぐ
名も知らぬ草に束の間しがみつき雨宝玉となりて輝く
流氷のように漂う此の世かと次々視界の変わるさびしさ
真っ赤な日沈み切るまで氷塊の上にて我も氷塊となる
流氷をめぐりて飛べる海鳥よ曇りてあれば響きつつ鳴く
目を開けてしまえば鳥は逃げて行く眠りの森の端に我がいる
紫陽花の葉に次々と落ちてくる雨あり木琴叩くがごとし
氷原が果てまで続くその果てに燃えつつ夕日今沈みゆく
生まれ死に生まれ死にして流氷の真っ赤に燃えるたまゆらにいる
地平線薔薇色に燃ゆ見る限り流氷原は鎮もりの中
流氷原心残りし墓標にて果てまで幾多の沈黙続く
今まさに離れんとする滴くあり命の重きかなしみが見ゆ
眠るたび死んでは朝に生まれくる命と思えば一日は楽し
流氷の間に間に位置を変えながら真っ赤に濡れて波輝きぬ
ものなべて虫の音となり燦々と星の輝く深夜となりぬ
森は羽 羽をひろげて森森とつめたき水の谷間をくだる
乾ききった泉のひそとよみがえる裡をかすめる鳥影あれば
水平線線の途絶えたあたりより波の数だけ鳥が飛びたつ
寂しくて浜を歩めば虚貝ふつふつとわがうつせを開く
星ふりて夜はつめたく流れいん水平線の見えるガラス戸
白い椅子浜辺にひとつふらふらと食べられそうに男がすわる
降りしきる雪の閉じられゆく窓とほのかにさびし我のうしろ背
春の土手輝く緑敷き詰めて踏めば小さな草立ち上がる
ゆっくりと沈みゆく日よ今日もまたあらゆる所に人の死がある
人の好い生徒がいつも引っ掛かる問題少しひねって作れば
死に向かう生も溶けゆく流氷も照らして斜陽かけらとなりぬ
新雪を踏めば大きく音のして命の一歩こだましてゆく
斜里岳の雪の形を見て決める種蒔き時あり土ほぐれゆく
幾重にも階積み上げて流氷のごとき都会が目のあたり見ゆ
(『夭折』『夜の大樹を』『流氷記抄・流氷記』よりとりあえず百首を書き出してみました)(2002年頃の試み)