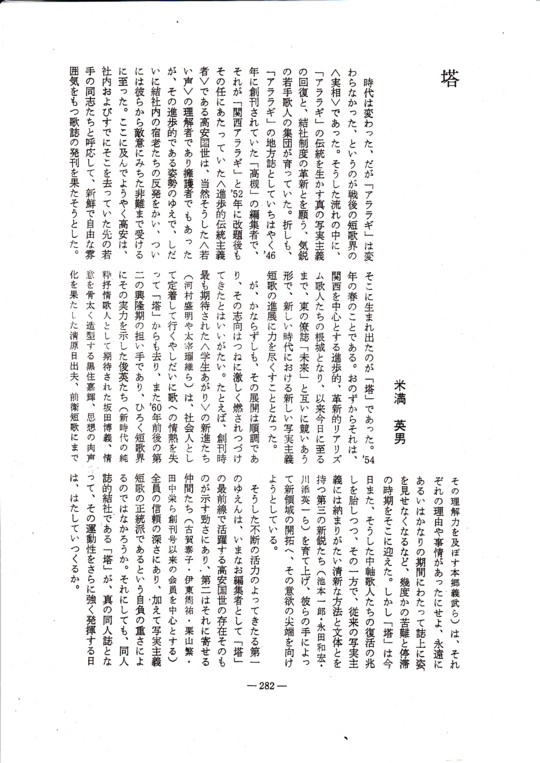短歌を作る子ども達
短歌を鑑賞する子ども達
浜 田 康 敬
毎年二月、私の住む宮崎市では若山牧水賞の授賞式が盛大に執り行われる。今年は小高賢氏の「本所・両国」と小島ゆかり氏の「希望」の二冊が同時受賞して、去る二月十二日その授賞式を終えた。
このことについてはすでに他のところで多くの人によって書かれているので今回、ここでは触れない。
さてこの若山牧水賞は今年五回目を記念して「全国子ども短歌コンクール」を同時開催し、当日発表された。
募集した作品は小学、中学、高校の部とに別けて発表されたが、たとえば
・桜咲く桜散ったよ桜舞う桜踏んだよ桜ごめん
は中学生の部の最優秀作品で、その自由でおおらかな表現は、我々大人歌人が、とても真似の出来ない部分である。
また
・先生に問題外と言われたら腐ってしまったオレの論文
は高校生の作品だが、この作者はおそらく、自分で短歌作品に表現したその瞬間「問題外」と先生に言われた自分のその論文が、とてつもなく大きな表現世界を獲得した手応えを感じたであろう。
学校の先生が問題外とした論文でも「腐ってしまう」と表現したことによって、作者は詩の核を確実に自分のものにした筈である。
ところで、短歌を作る子ども達は、この若山牧水賞のように公募機関も多く、最近よく見かけるようになったが、その一方で作品を鑑賞する子ども達のいることも、また私にはたいへん興味深く感じられることのひとつである。
大阪の高槻市から「流氷記」という、ポケットティッシュよりも一回り小さいサイズの歌誌だが、川添英一がほぼ一ヶ月半に一冊のペースで出している個人誌がある。
中綴じ本で毎号八十ページくらいのボリュームの歌誌だが、まず前の方のページには、藤本義一や落合恵子といった著名人が川添英一の前号作品評を丁寧に書いているが、作者の柔軟な詠風がこのような人達には馴染み易く受け入れられ、おおむね評判がいい。また歌人達も多く寄稿している。
私はしかしこの誌の中では、冊子後半ページの、どうやら川添英一の勤務する中学校の生徒達に書かせたものらしい、川添作品への批評が毎号、大変面白いことに注目している。
たとえば彼の次のような作品
・雪解けの冷たき水を飲みて咲く桜花びら星のごと降る
に対して「この号を読んでいてふと目に留まった一首だ。この一首を読んだ途端、その情景がありありと浮かんできた。その情景は正しく〈自然の美〉と呼ぶに相応しいものだった。この辺りではそのような美しい風景になど到底出会えるものではないが、想像するには難くなかった。今でもその情景を想像すると、私の心は「雪解けの冷たき水」で清らかに洗われているようだ」と評している。
また別の評者は「すごくきれいな一首だと思いました。ふだん私達は当たり前のように生きていて桜をただの植物だと思い、過ごしているけれど、桜にとってはすごく頑張って生きているし、雪解けの水も冷たく感じながらも飲んでいる。そして桜の花びらを星のように降らして私たちをなごませてくれます。そんな桜がとてもはかなげに感じました」とも書いている。
一つの作品をこのように評するこの中学生の文章は、この冊子の前の方に掲載されている大人達の評にも決して負けない作品評となっているのである。
もちろん川添英一の作品が書かせたものではあるのだが、なかなかに優れた批評文である。
もうひとつ引こう。
・我のみの歩む道あり表現の果てへ一筋足跡続く
という作品に対しては「真っ白な雪原を独りで‥‥という歌なのにちっとも寂しげな感じがしない。むしろ堂々としていて潔さがあると思う。表現の果てへ歩むことに迷いがなかったからか。そしてそれは一筋だけ続く足跡が示しているのだろう。素敵で、羨ましい歩み方だと思った」これも、とても中学生とは思えない。しっかりした考えのものに文章化した鑑賞である。
川添英一の作品を元にして、これらの文章を書いた本人達は、先の「問題外」と言われた論文作者と同じように、表現することによって今までとは違う世界の手触りを感じたに違いない。私は彼ら若い中学生達の、そこのところを信頼したいのだ。
それぞれが豊かに人間形成なされてゆく中で、書くこと作ることによってなにかを感じていくこと、それが詩であると自覚した時、そのことが更なる表現欲求へと駆りたててゆく、その繰り返しが一個の人格を形成していくのである。
ところで川添英一のことも少し紹介しておこう。
この誌「流氷記」という誌名からも伺えるが、作者の流氷に託す思いは並大抵ではない。
「網走に流氷接岸が報じられると居ても立ってもいられない気になる。今年は何とか網走に一日でも戻ってみたい」「‥‥網走の何かかいつも僕を駆り立てていて、創作の原点になっている」とは川添本人の言だが、その創作欲はすさまじい。
「流氷記」には毎号百十〜百五十首の作品を発表しているが、なかなかに精力的な作品数である。
作品は概ね平明で、中学生が読んでもわかり易い表現ではあるが、かといって詠われる世界は単純ではない。そういう意味からも川添英一という歌人はもっと評価されてもいい歌人であると私は思うのである。
(短歌総合新聞『ミューズ』平成13年第85号新緑号)

折々のうた 大岡 信
流氷が今日は離れて彷徨うと聞きて心も虚ろとなりぬ
川添英一
「流氷記」25号(平一三)所収。現在は大阪の茨木市で教師をするが、以前は北海道の網走市の第二中学校教師だった。そこの自然に感動し、「流氷記」の題で隔月の個人短歌誌を出し続け、すでに三十号を越える。「刑務所も二つ岩海岸も校区にて網走二中声太き子ら」「キタキツネ歩みしのみの流氷原その下にして育つ魚あり」。毎年早春ころ旧知を便りに網走を歴訪、歩き回るようで、その心の繋がりはまさしく第二の故郷。
(平成十五年三月二十八日) 注:二つ岩海岸=ノトルンワタラ
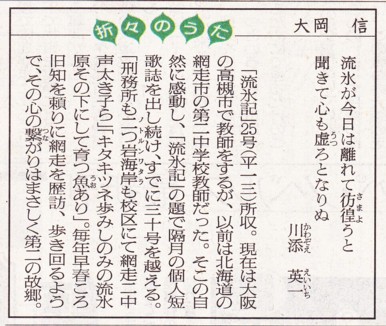


フランス語と翻訳
小原千賀子
je sous fou de vous
樹 水 風 土 母やわらかな闇打つしらべ忽然と乳房洗われてい 川添英一
この歌を読んだとき不思議な感じに魅了されると共に、何と美しくフランス語と日本語を組み合わせたことか、と驚嘆した。声に出すと ジュ スィ フ ドゥ ヴ、意味は「私はあなたに夢中です。」恋の歌だと思う。
私はフランス語が好きで、趣味で楽しく勉強していたのだが、いつの間にか翻訳のアルバイトをするようになり、「仕事になると、きついなあ」とつくづく実感している。
短編ひとつ訳し終へたる安らぎに昼少し前の図書館を出づ
高安國世
高安先生の翻訳を読んでみたいと思うが、果たせずにいる。言葉はまず声であり、音読してその調べを聞くことが何よりの楽しみ。短歌や詩の場合、それは愛誦生に通じてゆく。どんな言語も固有のリズムをもち、それが美しい。十二音節で詠われるフランス詩も三十一音の短歌も声に出して読んでゆきたい。 (『塔』二〇〇五年二月号)
歌集歌書を読む
三 枝 浩 樹
●川添英一歌集『流氷記』
著者はかつて高安國世のもとで『塔』の編集に携わっていた気鋭の人。現在、歌壇とは一線を画して掌中サイズの個人歌誌「流氷記」を発行している。本集はその集大成でユニークな分厚い文庫本となった。氏の第三歌集である。
もういいよ死んでもいいよと苦しみの母見て思う励ましながら
臨終のシーン幾度もよみがえり母が身近となりてしまいぬ
現身の母に隠れていた父の優しさ此の頃気づくことあり
残されし父の頑固を頼もしく思えて少し遺影と笑う
いい人を亡くしてほんとに寂しかね母がみんなの思い出になる
平明ながら深い味わいのあるこれらの挽歌。中学の先生をしている氏は自分の生徒たちに分かってもらえないような空しい歌は作るまい、と思ったのではないか。哀しみと微笑ましさと、そして生きてゆく勇気。そんな思いがそっと手渡される歌集である。
(総合雑誌『短歌』角川書店 二〇〇四年十二月号)
『詩歌の本棚』より
安 森 敏 隆
川添英一(大阪府高槻市)の『流氷記』(新葉館出版)は、二、三カ月に一回ずつ、友人知己に配られている豆本の歌をもとに纏めたユニークな文庫本形式の歌集である。
流氷に閉ざされいし海オホーツクブルーは深く息溜めて見る
網走に置き忘れてきた魂の在り処を捜す冬来たるべし
著者は、学生時代を京都で過ごし、高安國世に師事し、その後、網走二中に数年間勤務した体験と「流氷」をモチーフに短歌を創り続けてきた歌人である。ここでうたわれる「流氷」は、氏の魂の根源を志向している。「解説」にかえて、氏の豆本に「一首評」を寄せられた阿川弘之、北杜夫、田辺聖子、三浦光世等の評が何ともあたたかく、よい解説になっている。
(京都新聞二〇〇四年十月九日夕刊「ゆうかん文化」)
『詞華の森』より
櫟原聰
川添英一氏(大阪府高槻市)の『流氷記』(新葉館出版)は、手づくりの個人歌誌を文庫本にまとめたもの。「氷塊は一部屋ほどの大きさにぎっしり岸に積まれて並ぶ」と確かな存在感を刻みながら、「氷塊の上に座れば悲鳴とも怨嗟ともなき声こだまする」と、内なる声に耳を澄ませてもいる。平明な表現ながら、思いのよくこもる歌集である。
(朝日新聞二〇〇四年十月一日夕刊)
(余談)川添さんと中川のバッチャン
松田義久
川添さんが、流氷のまち網走にお出でになったのは昭和五十七年四月からのようです。川添さんにとっては初めての教員生活を遠くこの網走で経験を積むことになったようです。勤務先は網走市立第二中学校(国語教諭として)でした。当時の学校長は図らずも棚川音一氏で(一流歌人=『原始林』選者)彼を凡人として見ることは無かったと思います。早速、網走歌人会に引き込み腕を磨いていました。学校から見える流氷の広がりを見て虜になってしまったのでしょう。
それからの四年間というものは、学校の仕事を終えると、四季折々のオホーツク海を見て過ごしたのでは?そして、合気道に入門しているうちに、中川イセさん(通称〜中川のバッチャン)の存在を知り、遂には彼の後見人になってくださったらしい。そんな出会いで、知らない土地での仏様に会ったような中で、以降四年の生活はどんなにか楽しかったであろうと‥‥分かったように思います。四季折々の網走の景色が自ずから広がりノトロ牧場(中川さんの経営)へも足を伸ばすことも度々となり、更に女満別の方まで自然と向いていったようです。それなりに歌の範囲も広がり、今回の歌集にも載っているようです。
彼の作歌と言えば、小生とは違い、見ただけでも分かるようなテンポの速い、同景の連続です。殊に流氷記と銘打ちがあるだけ、一つ一つが生き生きしているのに驚かされます。その後、御家族の許へ帰られ、地元の生徒たちとも歌が広がっているようです。御尊母様を失い、その辺りの一連の作品も大したものです。ますますご健闘を祈っております。
(網走歌人会年刊歌集『氷花』第三五号二〇〇五年二月刊より)
〔時評〕個人誌歌集の楽しさ
長 岡 千 尋
大阪高槻市在住の川添英一氏は、縦十センチ、横六センチの手に乗るような豆本短歌個人誌を出し続けている。――その誌名は「流氷記」で、今夏、第四九号(思案夏)を発刊している。表紙裏・表ともにカラーで、八十ページ、本文の紙は明るいグレーと凝っている。いかにも手作りという感覚がお洒落で、全国の短歌誌はたくさんあるだろうけれども、これは川添氏だけの世界である。
氏は、二十歳で「塔」に入会、編集を担当するなどその才能を発揮し、池本一郎氏、永田和宏氏らとともに「塔の第三の新鋭」といわれた。しかし、「塔」の左翼的体質が嫌になり、「塔」の編集から離れ、歌壇から決別し、北海道へ移住している。―三十代半ばで再び復帰、現在は中学校の教師を務めながら、作家活動を続けている。
氏は多作で、毎号、百首近い作品を収めており、その努力を敬しつつ、私はいつも何かその憑かれたようなものに、衝き動かされるのである。ちなみに、この短歌誌のユニークな点は、毎号、氏の作品を、ジャンルを越えた名士に短評してもらっているといいうことだ。
四九号では、吉行和子氏(俳優)・中村桂子氏(科学者)・和田吾朗氏(俳人)・島田陽子氏(詩人)・三浦光世氏(三浦綾子文学館長)といった多士済々。歌人では米満英男氏・萩岡良博氏と私の知己も参加している。それ以前の旧号をめくっても、阿川弘之氏・北杜夫氏・藤本義一氏・田辺聖子氏・落合恵子氏などという著名人の名が出ており、川添氏の交際の深さに驚くわけだ。―それは別としても、氏のユニークさは、亡き母の知人、学校の保護者をはじめ以前、勤務していた中学校の教え子から、現在勤務する茨木市立西中学校の生徒の短評まで掲載されているということだ。だからこの個人誌は、氏の教育の場でもあり、教育者としての志と方法を模索した結果が、文学として表現されているということになろう。―一例だけあげてみる。
中二の女子のB・Rさんは、
・花びらはゴミとなりつつ桜散る瞬時瞬時が目に浮かびおり
を評して、桜には満開の時と、舞い散る時があるが、「私的には、舞い散る桜を見ている時のほうが、とても、綺麗だと感じます。」と率直な感想を記す。散ってゆく花の美しさを見た少女の情緒を、短歌が発見させたのである。私はこれを見て国語教育の大切さを思った。国語の乱れは、国の乱れであり、こんにちの社会問題でもあるが、川添氏のこの小さな言葉の力が、さざれ石を巌となすのである。―氏の作品をあげてみよう。
・色褪せて紫陽花開く傍を行く母の死いまだ鮮やかにして
・近づけば蓮池ざわと揺れてくる一瞬ありて鎮まり戻る
・逆さまに実は見ている目の部分持ちて奈落に吸われつつ寝る
・何時の日か私の私の視野も消ゆ映画のような日々と思えば
・原爆で亡くなりし蝉じりじりとあの夏伝う人揺れて見ゆ
・時止めて蝉の羽化やわらかく過ぐ今夜の眠りは月浮かべつつ
・電線に繋がれて立つ電柱を伝いて帰る独りの部屋に
〔『日本歌人』二〇〇六年十一月号より転載〕
塔 米 満 英 男
時代は変わった。だが「アララギ」は変わらなかった、というのが戦後の短歌界の〈実相〉であった。そうした流れの中に、「アララギ」の伝統を生かす真の写実主義の回復と、結社制度の革新とを願う、気鋭の若手歌人の集団が育っていた。折しも、「アララギ」の地方誌としていちはやく'46年に創刊されていた「高槻」の編集者で、それが「関西アララギ」と'52に改題後もその任にあたっていた〈進歩的伝統主義者〉である高安国世は、当然そうした〈若い声〉の理解者であり擁護者でもあったが、その進歩的である姿勢のゆえで、しだいに結社内の宿老たちの反発をかい、ついには彼らから敵意にみちた非難まで受けるに至った。ここに及んでようやく高安は、社内およびすでにそこを去っていた先の若手の同志たちと呼応して、新鮮で自由な雰囲気をもつ歌誌の発刊を果たそうとした。そこに生まれたのが「塔」であった。'54年の春のことである。おのずからそれは、関西を中心とする進歩的、革新的リアリズム歌人たちの根城となり、以来今日に至るまで、東の僚誌「未来」と互いに競いあう形で、新しい時代における新しい写実主義短歌の進展に力を尽くすこととなった。
が、かならずしも、その展開は順調であり、その志向はつねに激しく燃されつづけてきたとはいいがたい。たとえば、創刊時最も期待された〈学生あがり〉の新進たち(河村盛明や太宰瑠維ら)は、社会人として定着して行くやしだいに歌への情熱を失って「塔」からも去り、また'60年前後の第二の興隆期の担い手であり、ひろく短歌界にその実力を示した俊英たち(新時代の純粋抒情歌人として期待された坂田博義、情意を骨太く造型する黒住嘉輝、思想の肉声化を果たした清原日出夫、前衛短歌にまでその理解力を及ぼす本郷義武ら)は、それぞれの理由や事情があったにせよ、永遠にあるいはかなりの期間にわたって誌上に姿を見せなくなるなど、幾度かの苦難と停滞の時期をそこに迎えた。しかし「塔」は今日また、そうした中軸歌人ちの復活の兆しを胎しつつ、その一方で、従来の写実主義には納まりがたい清新な方法と文体とを持つ第三の新鋭たち(池本一郎・永田和宏・川添英一ら)を育て上げ、彼らの手によって新領域の開拓へ、その意欲の尖端を向けようとしている。
そうした不断の活力のよってきたる第一のゆえんは、いまなお編集者として「塔」の最前線で活躍する高安国世の存在そのものが示す剄さにあり、第二はそれに寄せる仲間たち(古賀泰子・伊東雋祐・栗山繁・田中栄ら創刊号以来の会員を中心とする)全員の信頼の深さにあり、加えて写実主義短歌の正統派であるという自負の重さによるのではなかろうか。それにしても、同人誌的結社である「塔」が、真の同人誌となって、その運動性をさらに強く発揮する日は、はたしていつ来るか。
(『現代短歌'74』282頁